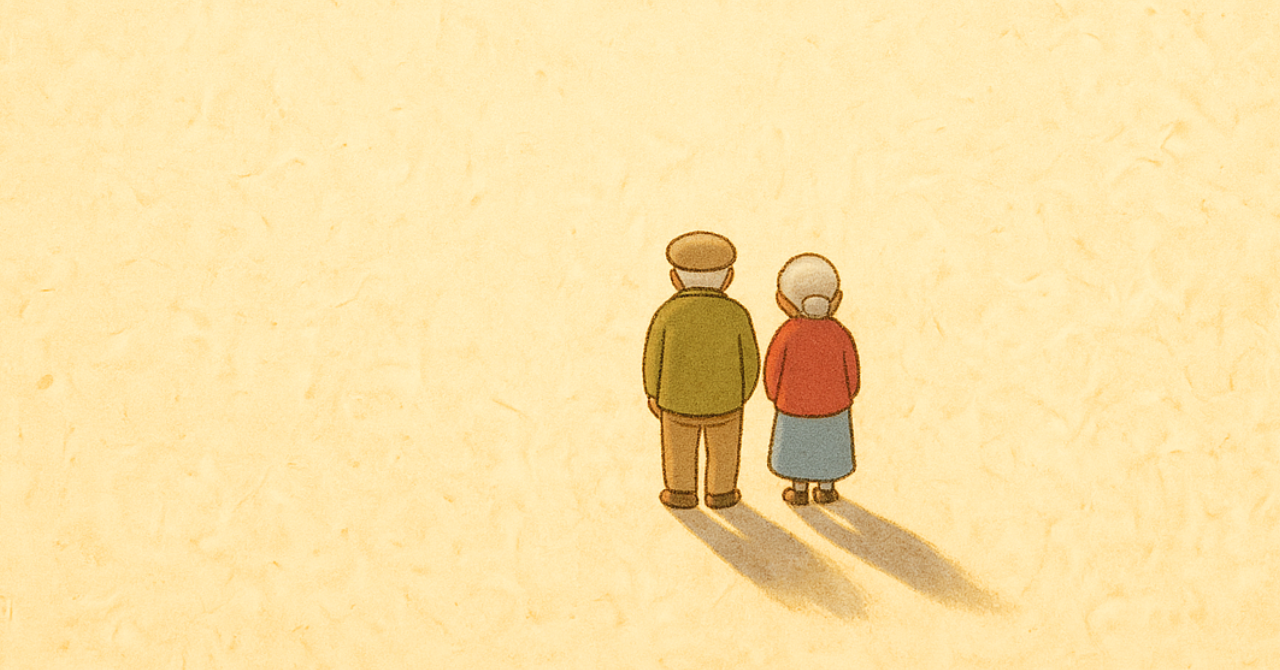YouTubeの旅動画で気づいた日本の所得の話。円安だけじゃない現実
私はYouTubeで旅系の動画を見るのが好きなのですが、海外の飲食店に入るシーンで「これ高くない?! やっぱり円安だなー」とyou tuberさんが話しているのをよく聞きます。あなたもそんな動画のワンシーンを見たことあるかもしれませんね。
最初は「円安で日本円が弱くなっているから仕方ないけど、なんかちょっと違和感が感じるよなぁ」と思っていました。私は普段、株をしているので、為替は毎日チェックしています。むかしからするとかなり円安だけど、為替の影響だけなのかな?とふと思ったのです。
10年前は1ドル=120円くらいなものが、現在では147円くらい。(2025年8月18日現在)
ちょっと計算してみたいと思います。
たとえばアメリカニューヨークの一風堂のラーメンが20ドルくらいなので、日本円にして2,940円。10年前の1ドル120円時代だったとしたら、2,400円。その差は540円あるけど、そもそも2,400円だってちょっと高すぎるでしょ!!と思うのです。
ですのでちょっと気になって調べてみたら、実は円安だけじゃないし、もっと根深い問題が日本にはあることに気づいたんです。
今日はその話をゆっくり、わかりやすく共有したいと思います。私も正直、少し悲しくなりました。けれど、知ることは大事ですよね。「高い!」の背景には何があるのか?
海外の物価が高いと感じるのは、上記のように円が弱くなっているのは事実です。
ただ、それだけで「海外の食事が高い」と感じるのは半分だけの理由かもしれません。なぜなら、アメリカやヨーロッパでは物価自体もここ数年かなり上がっているからです。つまり、ドルベースでも「値段が上がっている」わけですね。
そして何より重要なのが、日本の「賃金がほぼ上がっていない」こと。これがいわゆる「賃金停滞」です。
日本の賃金は本当に上がっていないのか?
総務省や厚労省のデータをみると、ここ20年の日本の実質賃金(インフレを考慮した後の賃金)はほぼ横ばいか、むしろ下がっている年もあります。
例えば、1995年頃と比べて2023年の実質賃金は数パーセントしか変わっていません。一方で物価はじわじわ上昇しているので、実感としては給料が減っている感覚が強い人も多いでしょう。
これに対してアメリカはどうかというと、インフレに伴って名目賃金も上がっています。ITや医療、金融など成長産業の賃金上昇が全体を押し上げているのです。
日本とアメリカの世帯年収中央値を比べてみました。
実は、「アメリカの収入は高い」とよく言われますが、具体的にどれくらい違うのか、数字で見るとわかりやすいです。
2023年のデータによると、
アメリカの世帯年収中央値は約 80,610ドル。
今の為替レート(約150円/ドル)で換算すると、約 1,200万円 になります。
一方で、日本の世帯年収中央値は約 560万円。
つまり、ざっくり言ってアメリカの典型的な世帯は日本の2倍以上の収入を得ている計算になるんです。
平均収入は、超富裕層がぐっと数字を押し上げていることが多いので、中央値(真ん中の世帯の収入)で比較するのがポイントです。上の数字は中央値なので、より「普通の人の収入感覚」に近いです。
さらに面白いのは、アメリカ国内でも州や都市によって収入に差があることです。
例えば、ニューヨーク州の世帯年収中央値は約 93,000ドル(約1,400万円)と高めですが、逆にミシシッピ州は約 53,000ドル(約800万円)程度とかなり低いです。
州ごとにこんなに違うんだということが理解できました。
日本は基本的に都道府県で多少差はあれど、ここまで大きく差がつくことはあまりありません。アメリカは州ごとの経済規模や産業構造の差が大きく、それが収入にも反映されているんですね。
また、日米の雇用形態の違いも平均収入に大きく影響を与えています。
「日本は非正規雇用が多い」とよく聞きますが、数字で見ると日本の非正規雇用率は約40%です。一方で、アメリカの「非正規雇用率」は一見4%程度と非常に低い数値となっています。
でもこれは、統計の定義が違うからなんです。
日本は「正社員以外のパート・アルバイト・契約社員・派遣社員」を全部非正規とカウントします。対してアメリカは「一時的な雇用で継続見込みがない仕事」だけを非正規としているので、パートタイムや独立請負などは別のカテゴリーで扱われています。
実際には、アメリカでも日本の定義に近い形で見ると非正規雇用率は20〜25%くらいになると推計されています。それでも日本とは2倍も違ってきていますね。
ただ、問題は割合以上に「質」にありそうです。
日本の非正規雇用は、賃金が低く昇進や正社員化が難しいなどの構造的な問題があります。これが若い人の将来の不安や所得停滞の一因と指摘されています。
一方でアメリカでは、パートタイムや契約社員でも賃金に差があまりないケースが多く、転職やキャリアチェンジが比較的しやすい環境もあります。
なぜ日本とアメリカでこんな差がついたのでしょうか。
これは経済構造や人口動態の違いが大きいです。
日本は1990年代のバブル崩壊後、長く経済成長が鈍化。人口も減少し、労働市場は硬直化しました。企業は内部留保を溜め込み、賃金を抑制し、非正規雇用を増やしました。
アメリカはITや金融、医療などの成長産業が経済を牽引し、人口も増加しています。労働市場は流動的で、多様な働き方を受け入れやすいのです。
まとめると、
YouTubeの旅動画で聞いた「高い!円安だな〜」の裏には、円安以外にも「日本の賃金停滞」や「労働環境の違い」が隠れている。
① アメリカの世帯年収中央値は日本の約2倍。これは超富裕層だけでなく中央値でも顕著。
② 非正規雇用率の違いは統計の定義によるもの。日本は約40%、アメリカは約20〜25%。
③ 経済成長や人口動態の違いが大きな差を生んだ。
④ 円安の影響も相まって、海外の物価は日本人にとってとても高く感じられる。
ここまで読んで、「なんだかモヤモヤするけど、少し見えてきた気がする」と感じてくれたら嬉しいです。私も調べてみて、「日本の所得問題って結構深刻な問題だな」と実感しました。
日本の賃金停滞の背景にあるもの
さて、ここからはなぜ日本の賃金が20年以上もほぼ横ばいなのか、その背景を少し掘り下げてみたいと思います。
①バブル崩壊後の長期停滞
1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、日本は「失われた30年」と呼ばれる長期の経済停滞期に入る。この間、企業の投資意欲は低下し、景気は低迷。物価がほぼ上がらず、実質賃金も伸び悩みました。
企業は業績が悪化したため賃金アップに慎重になり、結果として労働者の給与はほぼ横ばいに。
②非正規雇用の増加
同じ期間に非正規雇用が急増しました。非正規労働者は、正社員に比べて賃金が低く、昇進の機会も少ないため、平均賃金を押し下げる要因になっています。
1990年代初めは約20%程度だった非正規率が、今では約40%にまでに増加。
④労働市場の硬直性と雇用慣行
日本企業は長年、「終身雇用」や「年功序列」を基本にしてきましたが、これが逆に変化への対応を遅らせています。
労働市場が硬直的で、成果や能力に応じて柔軟に賃金を変える仕組みがあまり整っていません。結果として、生産性が上がっても賃金に反映されにくい構造が続いています。
⑤人口減少と高齢化
日本の人口は2008年頃をピークに減少に転じ、高齢化も急速に進んでいます。労働人口が減る中で経済全体の成長が鈍化し、賃金の上昇が抑制されるという負のスパイラルに陥っています。
⑥内部留保の積み上げ
企業は利益を社員に還元せず、内部留保(企業内に貯めたお金)を積み上げる傾向が強いです。これが賃上げ圧力を弱めているという指摘もあります。
アメリカの成長産業と労働市場の柔軟性
対照的にアメリカはどうでしょうか?
① IT・医療・金融の成長
アメリカ経済は2000年代以降、IT産業や医療、金融サービスが急成長し、これらの業界が高賃金を牽引しています。GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)をはじめとするテクノロジー企業の成功が賃金を押し上げている状況。
②労働市場の流動性
アメリカの労働市場は流動的で、転職が盛んです。職種や会社を変えやすく、実力や成果に応じて賃金が決まるケースが多いのも特徴。
③人口増加と多様な労働力
アメリカは人口が増え続けており、多様なバックグラウンドの人々が働いています。若年層の増加も労働市場を活発にしています。
まとめ 海外の「高い!」はこういった背景がある
旅系YouTuberの「高い!」というコメントは、一見単純な円安のせいに見えますが、実は賃金停滞や物価上昇、労働環境の違いが複雑に絡んでいるようです。
私たち日本人の生活実感と、世界の経済環境のギャップが垣間見える瞬間かもしれません。
最後に。
日本の賃金が上がらず生活が苦しいと感じる一方、世界の経済はどんどん変わっています。
社会全体としても労働市場の改革や経済成長戦略が急務です。
同時に私たちにできることは、こうした現実を知ったうえで、個人としてはスキルアップや投資、ライフスタイルの工夫が必須であるといえるかもしれません。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また気になるテーマがあれば記事にしていきますね。