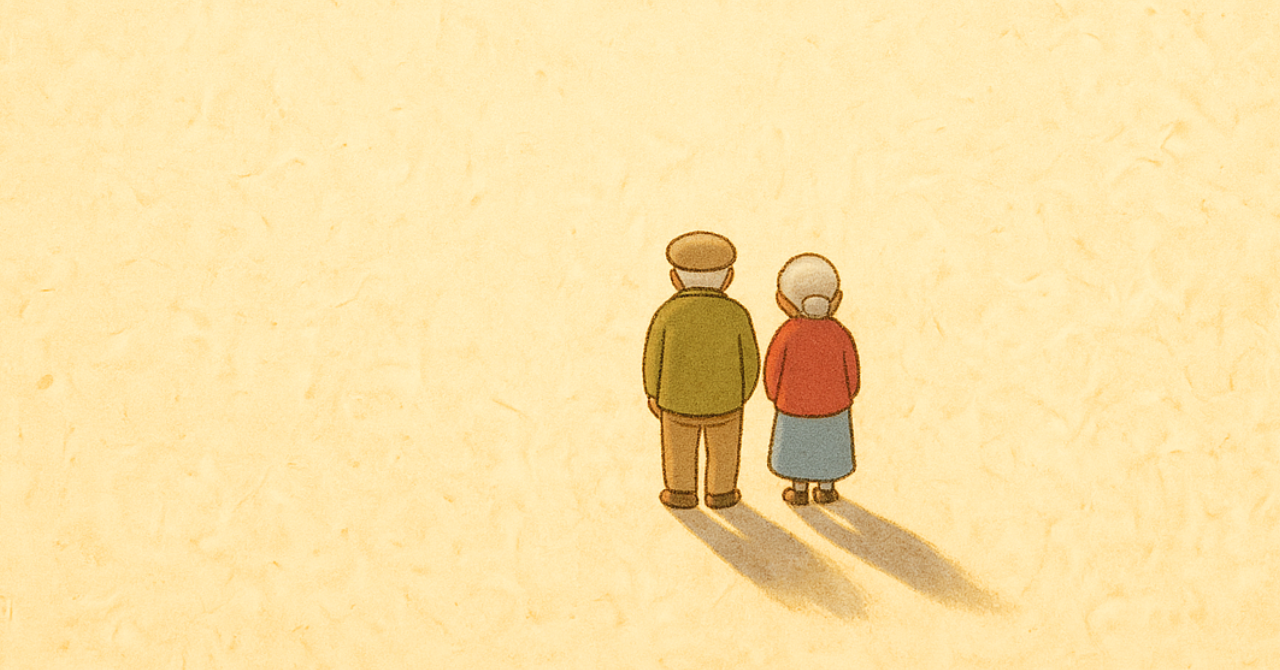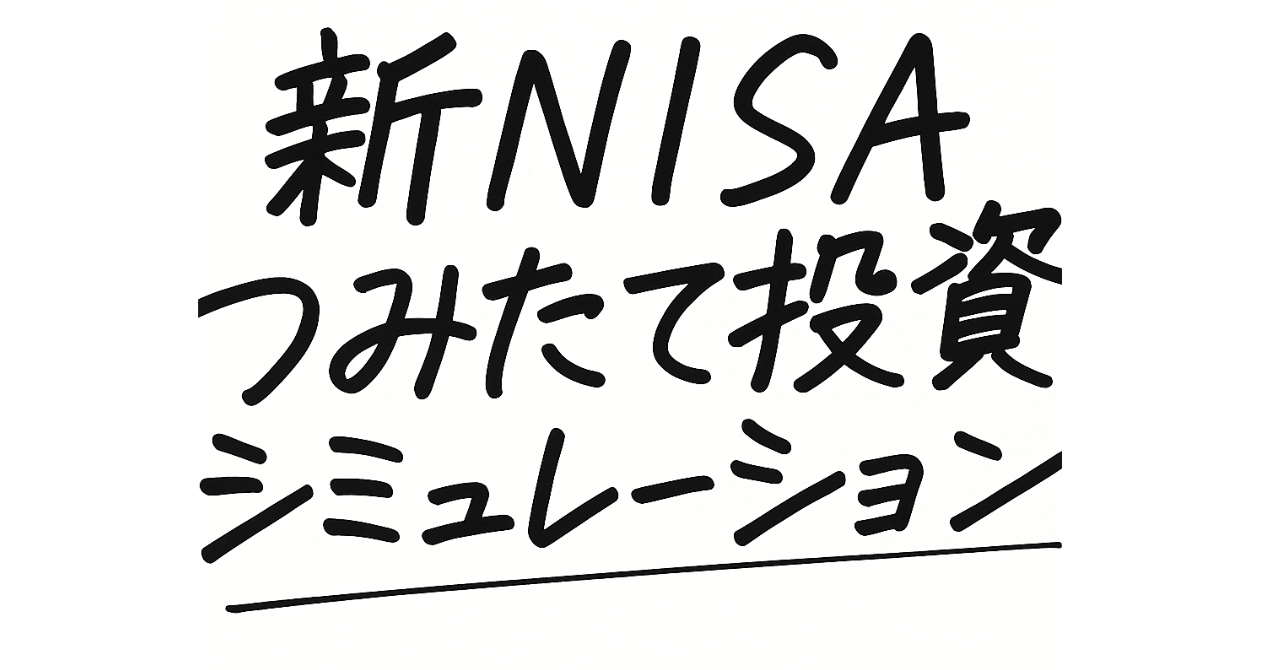FIREと年金、なぜ関係あるの?
「FIRE=もう老後は安心」ではない
FIRE(Financial Independence, Retire Early)という言葉、最近は本当に定着してきましたよね。
20代や30代から資産形成に励んで、40代や50代で仕事を辞め、あとは資産運用の利益で暮らす。そんな生活に憧れる人も多いはずです。
当然私もFIREの話題を目にすると、だいぶ日本人の価値観も多様化してきたなと痛感します。(私はFIREのFIをめざす一般投資家です)
でも、FIREの話になると、なぜかあまり触れられないものがあります。それが公的年金です。
SNSやYouTubeでは、「年金はもらえないからあてにするな」という声があふれています。確かに、将来の制度はどうなるかわかりません。支給開始年齢が上がったり、金額が減ったりする可能性はゼロではない。
だから「年金なんて計算に入れずに、すべて自分の資産でまかなう計画を立てる」というのは、一見すると安全策にも見えます。
しかし、ちょっと待ってください。
確かに安全といえるかもしれませんが、年金を完全に無視することでFIREというゴールが遠くなってしまいます。
FIRE後もずっと続く生活費の現実
FIREを考えるとき、まず必要なのは「毎月いくらで暮らせるか」の計算です。
例えば、生活費が月20万円なら年間240万円。
これを年利3%で運用しながら取り崩すとすると、FIRE開始時に必要な資産はおよそ8,000万円になります。
この8,000万円という数値のハードルは人によってとらえ方は違うのでしょうが、一般的に言ったら大金です。そのため、8,000万円をためるということがFIREのゴールとするのであれば、多くの人がFIREは遠い・・・と思わざるを得ません。
しかし、この金額を下げることが出来ればもっとFIREというゴールに近づくことが出来ます。
年金は『おまけ』ではなく『安全装置』
多くの人は、年金を「自分で稼げなかったときの保険」として考えていますが、本当はもっと積極的に使える資源です。
たとえば、同じ生活費20万円の人でも、65歳から月10万円の年金が入るなら、FIRE後に必要な資産額は一気に下がります。「資産だけで老後資金を全部まかなう」必要がなくなるからです。
逆に、50歳でリタイアしてしまうと、年金の受給額は大きく減ります。
これは加入期間が短くなる分、単純に計算しても年間で50万円近く差が出るケースがあります。
生涯で見ると、1,000万円近い差になることもあるのです。
この金額の差、FIRE後の生活に与える影響はかなり大きいと思いませんか?
「もらえないかもしれない」より「もらえたら心強い」
もちろん、「将来の年金制度は不透明」という不安はわかります。
私も「今の若い世代は、受給開始が70歳からになるかも」なんて話を聞くと、正直ドキッとします。
でも、制度がどう変わっても、全くゼロになる可能性はかなり低いと言われています。
公的年金は「毎年の仕送り方式+国庫負担+給付調整+運用収益」の組み合わせで維持されるため、制度そのものがゼロになる=破綻することは想定されていません。ただし、給付水準(もらえる額)が減る可能性はある、という点が現実的なリスクです。
だからこそ、「年金はないもの」と完全に切り捨てるのではなく、「ある程度はもらえるだろう」という前提で計画を立てるほうが現実的です。
もし年金が想定より減ったら、その分は資産から補えばいい。
でも逆に、想定通りもらえたら、その分だけ資産の取り崩しペースを抑えられます。
結果として、FIRE後の安心感は格段に上がります。
公的年金の基本をざっくり整理
さて、ここからは具体的に「公的年金って何なの?」という基本の部分を整理していきます。
年金って、制度が複雑でイメージしにくいせいか、「とりあえず毎月引かれているけど、どんな仕組みなのかはよくわからない」という人が多いですよね。
FIREを考えるときには、ここをざっくりでも理解しておくことがとても大事です。なぜなら、受け取れる額の見込みが立たないと、FIRE後の必要資産額が計算できないからです。
日本の公的年金は2階建て
日本の公的年金制度は、よく「2階建て構造」と表現されます。
1階部分 ★国民年金(老齢基礎年金)
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する基礎的な年金。
加入期間40年で満額をもらえる仕組みで、2025年度の満額は年額約79万2,000円(月額約6万6,000円)。
加入期間が短ければ、その割合に応じて減額されます。
2階部分 ★厚生年金(老齢厚生年金)
会社員や公務員などが加入する年金で、給与や賞与に応じて保険料が決まり、その分将来の受給額も増えます。
報酬比例と呼ばれる仕組みで、「どれだけの収入で何年加入していたか」が金額に直結します。
たとえば会社員として40年間フルに加入していた場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて、月額およそ14〜16万円程度になることが多いです(平均給与や加入期間によって上下します)。
自営業やフリーランスは1階建てが基本
FIRE後にフリーランスや自営業になると、厚生年金から国民年金のみの加入に切り替わります。
つまり、2階部分がなくなってしまうわけです。
すると、65歳からもらえる年金は、満額でも月額約6万6,000円程度。
「いやいや、これだけじゃ生活できないよ」と思う方も多いはず。
この差こそ、FIRE後の生活計画に大きく影響します。
50歳でFIREしてフリーランスになった場合、その後の15年間は国民年金のみの加入。
厚生年金の加入期間が短くなる分、将来の受給額は確実に減ります。
年金額の計算は「積み立て」ではなく「加入記録」
よくある誤解として、「年金は積み立てたお金がそのまま返ってくる」という考えがあります。
実際は積立方式ではなく、現役世代の保険料がその時点の受給者に支払われる「賦課方式」です。
でも、個人ごとの将来の受給額は、これまでの加入記録に基づいて計算されます。
厚生年金の場合、計算式はざっくりいうとこうなります。
報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 5.481 / 1000 × 加入月数
ここで「平均標準報酬月額」は、現役時代の給料の平均を指します。
たとえば平均月収30万円で40年間加入していれば、厚生年金部分だけで年額およそ88万円前後になります。
これに国民年金の満額(約79万円)を足すと、合計で年額167万円程度=月額約14万円になるわけです。
「加入年数」がとても重要
FIREを考えるときに盲点になるのが、この加入年数です。
加入期間が40年から35年に減るだけで、国民年金の満額部分が約5分の1減ります。
厚生年金も同様で、5年分の加入月数が減れば、その分だけ確実に受給額は減ります。
先ほどの例でいうと、
65歳まで働いた人:年額約168万円
50歳でリタイアした人:年額約119万円
差額は約49万円/年、生涯にすると1,000万円近くの差になることもあります。
年金制度は将来変わるかもしれないけれど…
さきほども触れましたが「どうせ将来は制度が変わるでしょ」という声もありますが、完全になくなる可能性は極めて低いです。
なぜなら、年金は国の社会保障制度の基盤だからです。
むしろ支給開始年齢の引き上げや給付額の調整など、少しずつ負担を分散する形で変化していくほうが現実的です。
だからこそ、FIREの計画を立てるときは、
「将来は減るかもしれないけど、ゼロにはならない」
という前提で数字を組み込み、その上で余裕を持たせるのが安全です。
50歳リタイアと65歳まで就業の差
前のパートで、公的年金の受給額は「加入期間」と「収入」に大きく左右されるという話をしました。
では、実際に50歳でリタイアした場合と、65歳まで働いた場合では、どれくらい差が出るのでしょうか?
数字で見ると、その差はかなりのインパクトがあります。
試算条件
ここでは、2025年度の制度と水準をベースに、シンプルな仮定で試算します。
平均月収(標準報酬月額):30万円
国民年金+厚生年金に加入
厚生年金加入期間: 50歳リタイア → 25年(20〜45歳まで厚生年金)+その後5年間は国民年金
65歳まで就業 → 45年(20〜65歳まで厚生年金)
国民年金は満額年額79.2万円を40年加入で受給(加入期間に応じて比例減額)
計算結果
50歳リタイア:年額 約118.6万円(月額 約9.9万円)
65歳まで就業:年額 約168.0万円(月額 約14.0万円)
差額:年額 約49.4万円(月額 約4.1万円)
つまり、毎月4万円以上の差が、生涯ずっと続くということです。
生涯で見た差
年金は一度受給が始まれば、亡くなるまで続きます。
仮に65歳から85歳までの20年間もらうとすると、差額はこうなります。
年間差額 49.4万円 × 20年 = 約988万円
およそ1,000万円の差です。
しかもこれは「現在価値」での話。物価上昇や長寿化を考えると、実際のインパクトはさらに大きくなります。
「月4万円の差」をどう見るか
FIREを目指す人の中には、「月4万円なんて、資産運用で簡単にカバーできる」と考える方もいるかもしれません。
たとえば年利3%で運用できるなら、月4万円(年48万円)を生み出すには1,600万円の運用資産が必要です。
言い換えると、50歳でリタイアする場合、65歳まで働く人に比べて年金差額を埋めるためだけに1,600万円多く用意しておく必要があるということです。
これはなかなか大きなハードルではないでしょうか。
FIRE計画における「年金の価値」
年金の差額は、ただの数字以上の意味を持ちます。
たとえば、65歳から毎月4万円多くもらえるなら、その分だけ資産の取り崩しを遅らせることが可能。
これは心理的にも大きな安心につながりますし、長生きリスク(資産が尽きるリスク)を下げる効果もありますね。
一方で、この差を軽く見ると、FIRE後に思わぬ資金不足に陥る可能性があります。
特にインフレや予期せぬ医療費が重なったとき、「年金が多いか少ないか」は生活の余裕を大きく左右するからです。
FIREは「経済的自由」を目指す素晴らしい考え方ですが、その計画の中に年金の現実的な数字を組み込むかどうかで、安心感も持続力も大きく変わります。
FIRE後の「年金空白期間」問題
50歳でリタイアする。
この響きは、多くの人にとって夢のように聞こえるかもしれません。
しかし、その夢には思わぬ落とし穴があります。
それが「年金空白期間」です。
年金空白期間とは?
年金空白期間とは、リタイア後から公的年金の受給が始まるまでの間、収入の柱が完全に途絶える期間のことを指します。
日本では原則65歳から老齢年金が支給されますので、50歳でリタイアすると15年間は自分の資産だけで生活費をまかなわなければなりません。
これは単純に生活費の問題だけでなく、心理的にも大きなプレッシャーになります。
なぜなら、この期間は資産を取り崩し続けながら、同時に運用リスクや物価上昇リスクにもさらされるからです。
具体的にどれだけ必要なのか?
仮に生活費を月25万円(年間300万円)としましょう。
50歳から65歳までの15年間で必要な生活費は、こうなります。
300万円 × 15年 = 4,500万円
つまり、50歳リタイアの時点で4,500万円は、最低限「生活費のためだけ」に確保しておく必要があります。
これに住宅ローンや教育費、突発的な医療費などが加われば、必要額はさらに膨らみます。
年金空白期間中のリスク
運用不調リスク
リタイア直後に大きな株価下落が起きると、資産価値が一気に減ります。FIRE初期にこれが起きると、その後の資産寿命に致命的な影響を与える「シーケンス・オブ・リターンリスク」に直面します。
物価上昇リスク
年金は一定の物価スライドがありますが、空白期間中は完全に自己資金頼みです。インフレ率が年間2%でも15年で生活費は約35%増えます。25万円が34万円に膨らむ計算です。
予期せぬ支出リスク
家の修繕や親の介護、自身の病気など、長期的に見れば想定外の支出はほぼ必ず発生します。これらは一時的に数百万円単位で資産を削る可能性があります。
年金空白期間を短くする方法
年金空白期間は、必ずしも15年である必要はありません。
以下の方法で短縮できます。
受給繰上げ
年金は60歳から繰上げ受給が可能です(ただし減額あり)。
繰上げ率は1カ月あたり0.4%(5年繰上げで24%減額)なので、慎重な判断が必要です。
生活費に困らない場合は避けるのが基本ですが、「資産温存のために一部期間だけ繰上げ」という選択もあります。
FIRE後も少し働く
週2〜3日のパートやフリーランス収入があるだけでも、資産取り崩し額を減らせます。
さらに厚生年金加入条件を満たせば将来の年金額も増やせるため、一石二鳥です。
支出の柔軟化
空白期間中は支出を抑える年と使う年をメリハリつけて管理する。
特に耐久消費財(家電や車)の買い替えは、相場や資産状況に合わせて調整します。
空白期間を甘く見ると…
年金空白期間を軽く考えると、思わぬ早さで資産が減ってしまうことがあります。
例えば4,500万円の資産を持っていても、
年間300万円の支出
年利2%で運用
という条件で15年間取り崩すと、残りは約2,500万円ほどになります。
そこから老後30年分をまかなうとなると、年金額が少ない場合は不安が残ります。
FIREと年金は「別の話」ではない
FIREの計画を立てるとき、「老後の年金はあてにしない」という考え方もあります。
確かに保守的な資金計画としては有効ですが、その場合は空白期間を含めて全期間分の生活費を自力で用意する必要があるため、必要資産額は跳ね上がります。
逆に、年金を正確に見積もって計画に組み込めば、必要資産額は大きく減ります。
特に厚生年金加入年数を減らさずに済む工夫をすると、FIRE後の安心感は格段に上がります。
年金を味方につけるFIRE設計
FIREを語るとき、多くの人が注目するのは「必要資産額」と「運用利回り」です。
しかし、長期的な生活設計においては、公的年金という第3の柱を軽視すべきではありません。
年金は、半永久的かつインフレ連動で支給される「生涯不労所得」です。これをうまく組み込むことで、FIREのハードルは下がり、リスク耐性も上がります。
年金は『保険』でもある
年金を単なる老後資金と見る人は多いですが、本質的には長生きリスクに対する保険です。
資産運用は寿命が延びれば延びるほど、資産切れのリスクを抱えます。
しかし、年金は生きている限り支給が続くため、どれだけ長生きしても生活費の一定部分をカバーしてくれます。これは株式や債券では再現できない特性です。
厚生年金を少しでも伸ばす工夫
FIRE計画では、できるだけ厚生年金加入期間を減らさないことがポイントになるでしょう。
理由は単純で、厚生年金は掛けた年数分だけ確実に将来の年金額が増えるからです。
50歳で完全リタイアせず、週3〜4日の時短勤務や契約社員に切り替えれば、厚生年金加入を続けられます。
収入は減っても、将来の年金増額と空白期間中の収入確保で、資産寿命が大きく延びます。
近年は週20時間以上勤務や一定収入以上のパートでも厚生年金に加入できる条件が広がっており、「少し働くだけでも年金が増える」時代になってきています。
年金額を前提に必要資産額を計算する
FIREの必要資産額については、よく知られている公式がありますよね。
(年間生活費 − 年金額) × 25倍(4%ルール)
例:年間生活費300万円、65歳以降の年金額が月15万円(年間180万円)の場合
(300万円 − 180万円) × 25倍 = 3,000万円
65歳以降の必要資産は3,000万円で済みます。つまり年金を見込めば、完全自力のFIREに比べて必要額を数千万円単位で減らすことが可能だということです。
また年金の繰り上げ・繰り下げを考えるのも戦略の一つです。
繰上げ(60〜64歳) 早くもらえるが1カ月ごとに0.4%減額。
長生きするほど損になる可能性が高い。
繰下げ(66〜75歳) 遅くもらう代わりに1カ月ごとに0.7%増額。
長生きリスクに備えるには有効。
FIRE後の資産と健康状態によって、戦略的に選択するのが賢いやり方です。
年金額を増やす以外の工夫
年金額を増やす以外の工夫には以下のようなものがあります。
物価連動を活かす
年金は物価や賃金の変動に応じて改定されます。
インフレ局面でも生活費の一部が自動的に上がるため、現金資産だけより安全です。
夫婦での受給最大化
配偶者の年金額も含めて世帯単位で計算すると、必要資産額がさらに減ります。
障害年金・遺族年金も知っておく
不測の事態が起きたときのセーフティネットとして機能します。
知識があるだけで選択肢が広がります。
この章の最後に。
「年金はもらえない」という悲観的な情報もありますが、現実的には制度は継続し、支給額は減ってもゼロにはなりません。
むしろFIRE後に生活が厳しくなったとき、年金があるかないかで安全度は大きく違います。完全に切り捨てるより、制度の現状と将来見通しを理解し、計画に組み込む方が合理的です。
まとめ 『年金はおまけ』じゃない
FIREという言葉は、「経済的自由を手に入れ、好きなときに仕事をやめられる」という希望に満ちています。
SNSやYouTubeでは、「〇千万円貯めればOK」「運用利回り〇%で生活できる」といったシンプルな図式がよく語られます。
しかし、実際に50代や60代を迎えてみると、もっと現実的で重要な要素が見えてきます。それが、公的年金というものです。
FIRE計画における年金の誤解
「年金なんてもらえない」
「支給開始年齢が上がるからあてにできない」
こうした声は少なくありません。確かに制度は変化しますし、将来の金額は減る可能性があります。
しかし、ゼロになる可能性は極めて低く、日本の年金制度は“長生きリスク対策”として設計されています。
つまり、制度が続く限り、一定額は生涯にわたり支給されます。これはFIRE後の生活にとって、非常に大きな安心材料ですよね。
年金は資産の延命装置
FIREに必要な資産を試算するとき、年金を考慮に入れないと「余分に数千万円多く」用意することになります。
たとえば、年間生活費が300万円の人が、年金を全く考慮せず4%ルールで計算すると、
300万円 × 25倍 = 7,500万円
という膨大な金額になります。
しかし、65歳以降に年間180万円の年金を見込めれば、
(300万円 − 180万円) × 25倍 = 3,000万円
で済みます。
差額は4,500万円。これだけでも、年金を“おまけ”と考えることがどれだけ非効率かわかります。
「空白期間」をどう生き抜くか
早期リタイア後、年金受給までの間に資産を食いつぶす「空白期間」は、多くのFIRE実践者にとって最大の課題です。
ここをどう乗り切るかで、FIREの成功と失敗が分かれます。
①空白期間を短くするために、50代後半までゆるく働く
②厚生年金加入を継続して年金額を底上げする
③資産運用と年金の組み合わせでキャッシュフローを安定させる
これらの工夫を組み込むことで、年金は『最後の砦』ではなく途中から効いてくる『強力な味方』になります。
年金は精神的安定剤でもある
資産運用だけで暮らす生活は、株価や金利に常に心を揺さぶられる可能性があります。
ところが、毎月15〜20万円の安定収入が生涯続くとわかっていれば、心理的なプレッシャーは大きく減ります。
FIREは「自由」だけでなく「安心」も追求するものです。その意味で、年金は数字以上に精神的価値の高い資産といえるでしょう。
「おまけ」から「柱」へ
FIREを計画する上で、年金を単なるおまけや余裕資金と考える人は多いですが、むしろ資産・運用・年金の三本柱で考えるほうが安定性は高まります。
資産は「即戦力」
運用は「成長エンジン」
年金は「生涯の安全装置」
この三つをどう組み合わせるかが、FIRE成功の鍵です。
本当の最後になります。m(__)m
長くなりましたが、最近とっても年金が気になります。それはそろそろ自分自身が定年というゴールが年々近づいてきているから。
FIREを実現するための公式は、資産額や運用利回りだけでは完結しません。
そこに年金という要素を正しく組み込むことで、必要資産額は現実的になり、計画の安全度は大きく高まります。
「年金はおまけじゃない」
むしろ、FIREを長期的に支えるための、欠かせない一本の柱なのです。